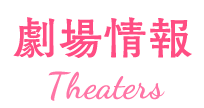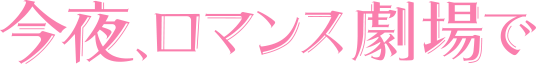9年の時を経て完成したオリジナル・ラブストーリー
『今夜、ロマンス劇場で』の発案は9年前に遡る。今の日本映画界は漫画や小説の実写化が多い中、「もっと映画館でしか楽しむことのできないオリジナルの物語があってもよいのではないか」と稲葉直人プロデューサーが思い立ったところからはじまる。その頃、映画『ハッピーフライト』を担当していた稲葉プロデューサーは、綾瀬はるかの唯一無二のコメディエンヌとしての才能に惚れ、「彼女の魅力をフル活用できるような映画を作りたい」と綾瀬はるかをヒロインとして企画を進めた。綾瀬はるかはきっとお姫様役がハマるという直感と、オリジナルで作るのであれば、漫画や小説では表現できない、映画だからこそ楽しめるストーリーでなくてはならないという視点から、バスター・キートン監督の『探偵学入門』や、そこからさらにインスパイアされたウディ・アレンの『カイロの紫のバラ』など名作の型をヒントに、白黒の古い映画、忘れ去られた映画からお姫様が飛び出してくるラブストーリーの軸が出来上がった。

武内英樹監督に託したコメディさとロマンティックさ
モノクロ映画の中から現実世界にお姫様が出てくる、という設定は、邦画としてはかなり突飛な設定だ。ラブストーリーをベースにしながら、前半はコミカルにテンポよく、中盤から物語が転調し、切ないラブストーリーになっていく。それをひとつの映画としてまとめられる監督は誰か──候補に挙がったのは、『のだめカンタービレ』や『テルマエ・ロマエ』シリーズの武内英樹監督だった。コメディを描くことに定評がある武内監督だが、実はそれ以上にロマンチストなのだと稲葉プロデューサーは語る。その武内監督は初めて脚本を読んだとき「美雪が触れられると消えてしまうことが分かってからの展開がとても切なく号泣した」と語り、その時点で素晴らしい作品になる予感がしたと言う。そして演出する際には、前半のコミカルさから後半のシリアスさへの温度調節に特に気を配ったと語っている。その後半へ転調していくスイッチとなるのは、ヒロインが抱える秘密だ。脚本作成の早い段階から秘密が恋の障害になることは決まっていたが、試行錯誤の末に脚本家の宇山佳佑と稲葉プロデューサーがたどり着いたのは、人に触れると消えてしまう設定。そして、映画のクライマックスのシーンは、好きだから触れたい、でも触れられない……葛藤する2人の姿に、観客の心を震わせる号泣必至の名シーンが生まれた。
綾瀬はるか&坂口健太郎、最強のベストカップル誕生!
ラブストーリーで観客を感動させるには、ストーリーの良さはもちろん、恋する2人のマッチング度が高くなければならない。綾瀬はるかとこの物語を奏でる相手役を探し続けた末、『ヒロイン失格』の坂口健太郎を見た稲葉プロデューサーは「ついにめぐり逢えた」と直感した。その映画で演じていたキャラクターと『今夜、ロマンス劇場で』の健司はまったく違うタイプではあるが、優しくて、繊細で、ちょっと情けなくて、純粋な心の持ち主、そんな健司を坂口健太郎ならきっと演じてくれるはずだとオファー。武内監督は「繊細な演技もさることながら、実はコメディセンスがものすごくある俳優」だと絶賛する。美雪と健司が初めて出会うシーンでもそのコメディセンスがよく現れている。美雪の映画『お転婆姫と三獣士』を観ている最中に突然の落雷、そして停電。暗闇の中で、映画の中から出てきた白黒の美雪と対面したときのリアクションや、出会ったばかりの美雪の尻に敷かれる感じなど、新しい坂口健太郎の一面が見られる。そして、綾瀬はるかに関しては「綾瀬はるか史上、一番美しい綾瀬はるかを撮りたい」と武内監督。モノクロの世界から飛び出してきたシーンは、顔はすすだらけで髪もぼさぼさであってもその美しさは際立っている。そこから色鮮やかな衣装を纏い、気高く魅力的な大人の女性に変身する。綾瀬が常に意識していたのは王女感だ。「体の軸をあまり動かさずに歩くとか、首の動かし方であるとか、王女らしさを忘れないようにしています」と語っていた。また、彼女は撮影現場のムードメーカーでもあり、「姫としての華やかさだけでなく、綾瀬さん自身が持っているパワーが華やか」だと坂口。綾瀬にいじられる坂口の姿も微笑ましく、この2人以外に美雪と健司は考えられないと思えるほどの最強のカップルが誕生した。

映画館も衣装もロケーションも徹底的にこだわったカラフルな色
タイトルにもなっている“ロマンス劇場”の舞台となったのは、栃木県足利市にある旧映画館・足利東映プラザ。約20年前に閉館となった劇場をレトロでカラフルな映画館に変貌させた。この映画の中でさまざまな“色”がちりばめられている象徴的な場所の一つとなっているが、モノクロの世界しか知らない美雪が初めて目にする場所が映画館のロビーだからこそ、彼女がときめくような、興味を示すような、カラフルな世界にする必要があったのだという。他にも美雪と健司のデートシーンの映像などは2人の恋が色づいていくにつれて画全体に鮮やかな色を配置するなど映画全体を通して色についての仕掛けがされている。また、美雪を演じる綾瀬が映画の中で着る衣装は、白黒のドレスも合わせると全部で25着にも及ぶ。選ばれた衣装にも、美雪の心情に合わせて色味を変化させていくなど、色の表現に徹底してこだわった。

ガラス越しのキスシーンは、あの名作映画へのオマージュ
「映画館を舞台にした映画を作るのであれば、映画愛に溢れたものにしたい」という稲葉プロデューサーの想いから、劇中ではさりげなく過去の名画へのオマージュがちりばめられている。映画に魅せられ映画監督を目指す健司と劇場館主の本多の関係性は『ニュー・シネマ・パラダイス』、そして映画の世界と現実の世界を繋ぐファンタジックな設定は『キートンの探偵学入門』『カイロの紫のバラ』、王女と身分違いの青年が恋に落ちるのは『ローマの休日』、落雷によって変化が起きる設定は『バック・トゥ・ザ・フューチャー』、劇中劇「お転婆姫と三獣士」のモデルは『オズの魔法使い』『狸御殿』シリーズ、北村一輝が演じるスター俳優・俊藤龍之介の愛称“ハンサムガイ”は日活のガイシリーズ……など、全く同じシチュエーションということではなく、それぞれの映画のエッセンスが上手く物語にとけ込んでいる。なかでも特に印象的なのは、美雪と健司のガラス越しのキスシーンだろう。これは『また逢う日まで』のオマージュなのだが、触れたいけれど触れられない2人というこの映画の設定にうまく活かされ、とてもピュアで美しいシーンとなった。また、この映画の時代設定が1960年であることにも理由がある。それは、映画からテレビへと変わりゆく時代だったということ。カラーテレビの放送が始まったのが1958年。1960年は映画の観客数が急激に減り始めるまさに転換期だった。時代の変化とともに皆の記憶から忘れられていった映画たち。本作ではそんな映画たちへの想いが込められている。