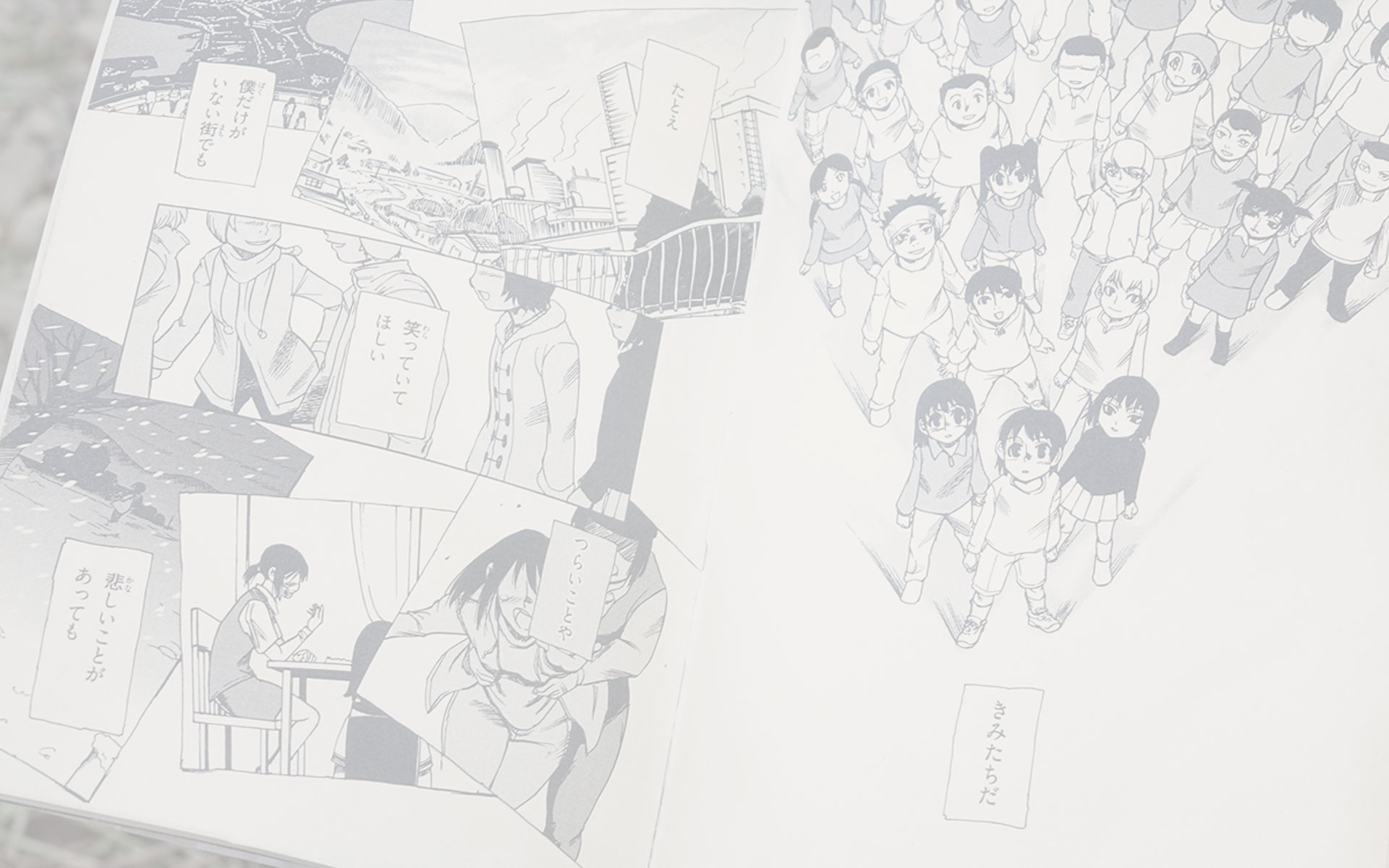2013年春、朝日新聞に掲載されていた書評を読んだ春名慶プロデューサーは、『僕だけがいない街』というタイトルと、タイムリープというSF的な内容のギャップに惹きつけられて、すぐに第1巻を取り寄せた。「冒頭から、こんなに強烈に引き込まれる作品にはなかなか出会えない。1度読み始めたら、この先どうなるんだろう? と、ページを捲る手が止められませんでした」。すぐに映画化を思案し始めた春名は、「これは子役の演技が重要な映画になる」と思い、TVドラマ「白夜行」(06)や、自身のプロデュース作『そのときは彼によろしく』(07)で子役の芝居をつくる技術の高さに信頼をおく平川雄一朗監督の顔を思い浮かべた。平川は春名から食事の席で原作コミックを渡された時、すでにそれを読んでいたため、作品との運命的な繋がりを感じたという。「僕も原作を読んで、雛月という女の子を取り巻く人間ドラマと、1988年という時代設定やリバイバルという装置が面白くて、これは映画にできると思っていたんです」。春名はその直後にKADOKAWAの編集者に平川監督での映画化を正式にオファーする。非常にスムーズな始動だった。
原作者・三部けいは、実写映画化に対して非常に協力的で、すべてを制作チームに一任した。しかし、原作はまだ連載中で、いくつもの謎と伏線が散りばめられた状態だったため、春名は三部に対して〈質問会〉の開催をリクエストした。「連載が終わる前に脚本を作って映画化するためだけでなく、原作のファンの1人、読者の1人として、たくさんの疑問がありました」。春名が投げた質問リストは約40項目以上。春名の原作の読み込み方が三部の想像を超えており、制作チームの熱量も伝わった得るものの大きいキックオフとなった。
春名は『神様のカルテ』シリーズで共に仕事をし、TVシリーズの「チームバチスタの栄光」などでも丁寧かつ緻密なミステリーの仕立てが光った後藤法子に脚本をオファー。課題はやはり、原作が完結していない作品をどうラストまで着地させるか。その手がかりは、三部が春名に宛てた6枚のメモ用紙だった。「三部さんは、ラストのアイデアと、それらに向けての複数のルート案を描いていました。映画の尺のなかで、原作とは違うオリジナルのラストを作ることになり、伏線やルートもオリジナルで張りめぐらせることを後藤さんにお願いしました」。脚本づくりには平川も加わった。原作の設定や世界観を踏襲しながら、ある地点から道なき土地にレールを敷くという難易度の高い作業において、道標となったのは春名の「悲劇でもいいんじゃないか」という言葉だった。タイムリープものは過去を変えると未来が変わる。過去のしくじりを良い方向に変換するにあたり、得られるものがあるならば、それと引き換えに何かを失い、プラスマイナス0になる。「『僕だけがいない街』とは何を意味するのか? 2人の命を救うならば、その代償は相当大きなものであるべきだと思い、担当編集者に相談したら同意してくれました。これにより、SFというジャンルを愛する人たちが大切にするルールを担保できたと思います」。平川は「悲劇でも単なる絶望では終わらず、ラストで希望を描いてほしい」と後藤にリクエストし、何度もやりとりを重ねた結果、後藤から映画オリジナルの名エンディングシーンが誕生した。
春名は原作を読みながら自然と、悟に藤原竜也の顔を、愛梨に有村架純の顔を重ねていたという。「観客が観たい藤原竜也は、『カイジ』や『藁の楯』のような異能・異端なキャラクターです。しかし、近年の藤原竜也は『神様のカルテ2』のような地に足の着いた演技でも魅力を放つようになっています。悟というキャラクターは、売れない漫画家という未完成で平凡な男ですが、リバイバルという出来事に巻き込まれる彼の人生は非凡。観客のニーズと本人の資質をうまくミックスできる役だと思いました」。プロットも台本もない初期段階に、春名は藤原のマネージャーに「とにかく読んでみて」と原作を渡したところ、藤原サイドは出演を快諾する。愛梨役の有村架純サイドにも、春名は同様の手法でオファーをしたところ、やはり快諾。春名は「理屈抜きに続きを読みたくなる面白さだから」と、キャスティングの成功には原作の力が大きかったと述懐する。2人の年齢もあり、春名は「原作の完コピはしない」という方向性を明示した。「悟と愛梨の関係にラブストーリー的な要素を入れ込みたくて、33歳の藤原竜也が演じる悟が、女子高生の愛梨と……となると生っぽくなってしまうので、愛梨を夢追うフリーターという設定にしました」。
雛月加代役にはTVドラマ「八重の桜」「Woman」などで、すでにその演技力が注目されていた鈴木梨央を春名がキャスティングした。一方、悟役は、藤原竜也に似ていることが重要だった。オーディションで抜擢されたのは、本格的な芝居はこれが初めての中川翼。「演技はほぼ未経験ですし、梨央ちゃんよりも1歳下なので、周りとくらべても未熟でした。29歳の男が乗り移った10歳の男の子というものすごく難しい役を演じられるのか、ちょっとだけ不安でしたが、リハーサルをちゃんとすればなんとかなると思いました」と平川監督はキャスティングの理由を振り返る。案の定、顔合わせの時、1番頼りなかった中川だった。それが、リハーサルを重ねてクランクインを迎えた時には周りが驚くほどの成長を遂げ、現場でしっかり中心に立っていた。彼にとって1番の課題は、恥ずかしいという気持ちを取り払うことだった。そのために平川監督はリハーサルで中川に「コマネチ!」というギャグを全力でやらせた。最初は恥ずかしそうだったものの、いつしか平気で「コマネチ!」とできるようになり、撮影現場でも、同級生を演じた子役たちと、「コマネチ!」「コマネチ!」とやり合い、ゲラゲラと笑い合う姿が見受けられた。また、当初は全然声が出ていなかった中川は、自宅でバランスボールに乗って発声練習をした結果、誰よりも大きな声を出せるようになっていたという。藤原の出演作品の鑑賞を宿題に出された中川は、課題作品をすべて観て、その演技力を尊敬するように。顔合わせでビーチサンダルを履いていた藤原への憧れから、肌寒い地方ロケでもビーチサンダルを履き続けていたという。
平川は、藤原と有村のキャスティングを受けて、悟と愛梨の関係を「恋仲まではいかないけれど、お互いがお互いを必要とする存在なので、自分に持っていないものを相手が持っているがゆえに引き付け合う関係にしたかった」と演出のポイントを語る。平川は、感情を出さず他人を寄せ付けない悟を演じる藤原には感情を抑えた芝居を、愛梨の積極性や前向きな姿勢を表現するために有村には大きな芝居を要求した。春名は愛梨という役について「原作の愛梨像を拡大解釈し、どこかで悟を導くメンター的なポジションを与えたので、所在の置き方やキャラクターの作り方が難しかったと思います」と解説する。有村は原作にある愛梨の漫画的なしぐさや、正義の味方ポーズに通じる手の見せ方などを、平川と模索しながらキャラクターを作り上げていったという。平川は「自分でこうだと決めつけず、いろいろな可能性からベストを探す努力を惜しまない、いい女優さんだと思います」と、有村の真摯な姿勢を絶賛する。本作のスケジュールは、2006年パートを先に、続いて1988年パートを撮影した。そうすることで、中川は藤原の現場を見学して「自分に乗り移るキャラクター」を実感してから自分の撮影に取り組むことができた。また、雛月役の鈴木梨央は、現場でふとした瞬間に、スマホを見ている姿が見受けられた。何を見ていたのかというと、原作漫画の雛月の表情だったという研究熱心さ。鈴木は平川に、「追い込まれたいから簡単にOKしないでほしい」とリクエストしたという。実際、「言えば言うだけどんどん良くなった」と、平川は証言する。子役への演出は時間がかかるため、共演する俳優たちには忍耐力が求められる。石田ゆり子や及川光博は何一つ不平を言わないどころか、石田に至っては監督に「私も追い込んでほしい」とリクエストしたという。
2006年パートで悟が暮らす街は、原作の舞台の一つでもある千葉県船橋市でロケを行った。「ロケハンをしたら、あの雑多な感じが現代の混沌とした世界、人間の欲望に溢れた街を表現するのにぴったりだと思いました」と平川は言うが、その雑多=ごちゃごちゃしている街での撮影は、人通りも多く、簡単ではなかった。また、2006年パートで泣かされたのが、天候不順。晴れてほしい日には雨が振り、雨が降ってほしい日には晴れるという不運が続き、何も撮れない日が発生しながらも、スケジュールをやりくりした。逆に、1988年パートは天候に恵まれた。2006年の船橋と対になる場所として、時間をかけてロケハンを行った。原作の舞台は北海道だが、主なロケ地となる小学校が長野県伊那市に見つかったため、そこに合わせて昭和の風景が残る街を探してロケを行った。
起きていることは非日常だが、あくまでも日常的な風景のなかでストーリーが進行する本作において、CGもまたリアルな日常を作り出すことが求められた。原作の風景を表現するために欠かせない雪も、スタッフによって妥協することなく創りだされた。劇伴は、ドラマ「ストロベリーナイト」の林ゆうきに春名がオファーした。協働した『神様のカルテ2』『アオハライド』で林の生み出すリリカルな音楽に注目した春名は、作品の持つ叙情性とミステリー性、日常と非日常性を、メロディだけでなく音像で表現できるのは林だと確信。平川は本作が描く人間の温かみや哀しみを打ち出すために、「泣ける」という要素をリクエストした。林は2人の要求に見事に応える劇伴を完成させた。