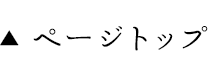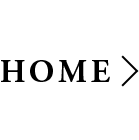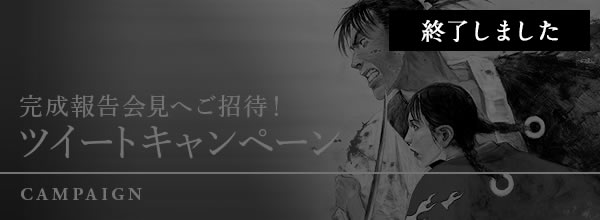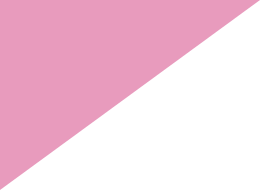2015年11月、クランクイン。その日の撮影が終わったとき、木村拓哉と杉咲花はごく自然にハイタッチした。ふたりの心が通い合った瞬間だった。
「杉咲さん演じる町と凜は、きっとクランクアップまで万次の生きる意味になると自分は思っていました。クランクインしてみて、(お互い)言葉にしなくても、その空気感のベースは構築できたかなと思いますね。クランクインって、すごく大事じゃないですか。それで、自分も(知らず知らずのうちに)そういう態度に出てしまったのかもしれませんね。それは<契り>ということだったのだと思います。お前がいる限り、自分も存在できる……というか。自分と杉咲さんのあいだの契りなのか、万次と凜のあいだの契りなのか。両方あった気がします。むしろ、そこは変化を持たせる必要もなかった。自分と杉咲さん(の距離感)は、作品の中の万次と凜に近いと思いますね。万次を作り上げるというよりは、杉咲花ちゃんが演じてくれた町であったり、凜ちゃんだったりを感じて、自分の表現に変換させていただきました。彼女が苦しめば苦しむほど、万次としてはアクセルの回転数があがる。小柄な彼女ですけど、杉咲さんの存在は僕の中では、すごく大きな存在でしたね」
そして撮影初日の三池崇史監督の演出を次のように語る。
「クランクインはロケでしたが、そのときに三池監督からは、こうしてください、ああしてください、ここに佇んでください、というディレクションは一切なくて。その日の撮影が終わります、というときに、三池監督が『万次に今日、逢えたので良かったです。お疲れさまでした』と――気づいたら、撮影が(すべて)終わって、クランクアップしていました。一度もディレクションしていただかなかったという印象ですね」
三池監督は、木村との顔合わせについて、こう振り返る。
「非日常的な物語を作っている分だけ、リアルな木村拓哉という人物を逆に感じることができたと思います。自分のようなエンターテインメントを作っているような人間からしたら夢ですよね。母親もびっくりしていますからね。『木村拓哉? あんた、もうアガリじゃない』みたいな感じで(笑)。80いくつのおじいちゃん、おばあちゃんでもそう思うっていう。その人間と一緒にものを作っていけた。(映画が)ただごとで終わったら申し訳ないですよね」
真冬、極寒の京都。屋外が中心の撮影となったが、木村は「三池組に参加させていただいてるという喜びが、痛さや寒さを二の次にさせてくれた」と力説する。
「スタッフに対する言葉選びに気遣いを感じます。緊張感あふれる現場はもちろん素敵ですが、それだけではパンクしてしまう。そういうとき、三池監督は、わざとガス抜きするんです。たとえば、パンクを防ぐための冗談を言う。関西の方なのでツッコミ的なものを現場に放ってくれます。そこに三池監督の繊細な部分を感じます。あと、海外にいるような感覚を受けました。日本人の感覚の枠ではないというか。ちょっとはみ出しているところを随所に感じました」
そして、こう付け加える。
「僕は殺陣とか立ち回りという言い回しがあまり好きではないんですが、たとえば、たくさんの人たちが殺められ絶命するシーンの撮影の前に監督はこんなふうに説明するんです。『みなさん、いまから撮るシーンはあくまでも殺し合いなので、くれぐれもそういう趣で本番を迎えてください』。このワードが出たときに、自分と同じ感覚の人がいてくれる、ワンシーン、ワンカットを見てくれている。それがわかって非常にドキドキしたし、嬉しかったですね」
「杉咲さん演じる町と凜は、きっとクランクアップまで万次の生きる意味になると自分は思っていました。クランクインしてみて、(お互い)言葉にしなくても、その空気感のベースは構築できたかなと思いますね。クランクインって、すごく大事じゃないですか。それで、自分も(知らず知らずのうちに)そういう態度に出てしまったのかもしれませんね。それは<契り>ということだったのだと思います。お前がいる限り、自分も存在できる……というか。自分と杉咲さんのあいだの契りなのか、万次と凜のあいだの契りなのか。両方あった気がします。むしろ、そこは変化を持たせる必要もなかった。自分と杉咲さん(の距離感)は、作品の中の万次と凜に近いと思いますね。万次を作り上げるというよりは、杉咲花ちゃんが演じてくれた町であったり、凜ちゃんだったりを感じて、自分の表現に変換させていただきました。彼女が苦しめば苦しむほど、万次としてはアクセルの回転数があがる。小柄な彼女ですけど、杉咲さんの存在は僕の中では、すごく大きな存在でしたね」
そして撮影初日の三池崇史監督の演出を次のように語る。
「クランクインはロケでしたが、そのときに三池監督からは、こうしてください、ああしてください、ここに佇んでください、というディレクションは一切なくて。その日の撮影が終わります、というときに、三池監督が『万次に今日、逢えたので良かったです。お疲れさまでした』と――気づいたら、撮影が(すべて)終わって、クランクアップしていました。一度もディレクションしていただかなかったという印象ですね」
三池監督は、木村との顔合わせについて、こう振り返る。
「非日常的な物語を作っている分だけ、リアルな木村拓哉という人物を逆に感じることができたと思います。自分のようなエンターテインメントを作っているような人間からしたら夢ですよね。母親もびっくりしていますからね。『木村拓哉? あんた、もうアガリじゃない』みたいな感じで(笑)。80いくつのおじいちゃん、おばあちゃんでもそう思うっていう。その人間と一緒にものを作っていけた。(映画が)ただごとで終わったら申し訳ないですよね」
真冬、極寒の京都。屋外が中心の撮影となったが、木村は「三池組に参加させていただいてるという喜びが、痛さや寒さを二の次にさせてくれた」と力説する。
「スタッフに対する言葉選びに気遣いを感じます。緊張感あふれる現場はもちろん素敵ですが、それだけではパンクしてしまう。そういうとき、三池監督は、わざとガス抜きするんです。たとえば、パンクを防ぐための冗談を言う。関西の方なのでツッコミ的なものを現場に放ってくれます。そこに三池監督の繊細な部分を感じます。あと、海外にいるような感覚を受けました。日本人の感覚の枠ではないというか。ちょっとはみ出しているところを随所に感じました」
そして、こう付け加える。
「僕は殺陣とか立ち回りという言い回しがあまり好きではないんですが、たとえば、たくさんの人たちが殺められ絶命するシーンの撮影の前に監督はこんなふうに説明するんです。『みなさん、いまから撮るシーンはあくまでも殺し合いなので、くれぐれもそういう趣で本番を迎えてください』。このワードが出たときに、自分と同じ感覚の人がいてくれる、ワンシーン、ワンカットを見てくれている。それがわかって非常にドキドキしたし、嬉しかったですね」


木村の姿勢を、監督はこう言い切る。
「コツコツなんですよね。ひとつひとつに全力で。映画的に言うと、作品の7割ぐらいは後ろ姿もあるし、目を開いていても大丈夫なカットがあるのに、朝5時半にメイクをしてから夜まで、夜中になることもあるわけですが、ずーっと目を瞑っている。ご飯のときも含めて。普通なら芝居どころじゃなくなると思う。でも彼は『だって、万次はそうだから』と続ける。しかも、片目での立ち回りだから、距離感がとりづらい。(本来であれば)危なくって無理だよね。それを『だって、万次だから』でやる。ずっと裸足というのもありえないですよ。地下足袋履いてもわからないシーンでも、そういうこと関係なしに、ずっと裸足に草履だけで条件の悪いところでもやっている。クタクタになりながら。それが本当に驚きですよ。素晴らしいですね」
主人公、万次は、どこか木村拓哉その人に重なる気がする。監督はこう指摘する。
「確かに似ていますね。本人がどういうふうに感じて、どう思ってるかわからないですが、自分からすると非常に運命的な役だと思います。(木村と万次は)まったく違うところで生まれ育ってるわけですが、この世の中で同じ空気は吸って生きているのでリンクするってことがあるんだなと思いました。そいういうものと出逢っていく強さがやっぱり必要ですよね。(木村は)すごく特殊で、日本で唯一スーパースターと言える人物だと思いますが、そういう強さがなければ、いま、このようにはできていないはずです」
そして、木村を含めたキャスト全員について話す。
「ただ素敵なだけでは、ただ綺麗なだけでは、役者としてうまく生きていけないだろうと思います。たとえば、ロケの寒い中でやっているほうが、ドキッとする表情を見せたりするんですよね。それはつまり、動物的なところを持っているということだと思うんです。そういうなにか、生きものの強さというものに、僕ら(スタッフ)は撮っているときに助けられる」
動物的といえば、万次の在り方はまさにそうだ。木村は、こんなふうに表現した。
「相手が強ければ強いほど、牙を剥くだろうし、爪も立てるだろうし。ほんとうに動物に近い対応だと思います。ものすごく大きいのは、万次が凜の中に町を感じていたこと。凜を初めて見たときに、町とオーバーラップしてなかったら、あそこまでくいしばって立ち続けることはできなかったと思います。自分が死なせてしまった妹を凜に重ね合わせていたからこそ、そうすることができた。ビジュアルって大事ですね(笑)。ものすごく特別なケースだとは思いますが、土壇場を五万と経験している万次のような人ほど、そんなことにもなるような気がします」
凄まじい活劇が繰り広げられる本作。それは生命を映し出す鏡でもある。監督は言う。
「血は忌まわしいものと捉えられがちだけど、結局は生きている証でもある。暴力って美しいものでもないし、否定すべきものなのでしょうが、その瞬間になにか光るものがあって、どうしても逃れられない人間の本質というか、動物として地球で生きていくための本当の姿が、時代劇では平気で出せるんですよね。ギラギラと。斬り合っていい世界なので」
つまり、『無限の住人』はただの一風変わったフィクションではない。現代を生きるわたしたちにも通じる「何か」が描かれているのだ。
最後に、木村が考える<無限>の意味を訊いた。
「ぼんやり思うことですが、それは<時間>や<時空>ということではなく、<想い>なんじゃないかと。感情ではなく<想い>。個人が抱くことができる<想い>。むしろ、なんで<永遠>って言わないんだろうと思いますけどね。漢字では<限り無き>の<無限>ですからね」
「コツコツなんですよね。ひとつひとつに全力で。映画的に言うと、作品の7割ぐらいは後ろ姿もあるし、目を開いていても大丈夫なカットがあるのに、朝5時半にメイクをしてから夜まで、夜中になることもあるわけですが、ずーっと目を瞑っている。ご飯のときも含めて。普通なら芝居どころじゃなくなると思う。でも彼は『だって、万次はそうだから』と続ける。しかも、片目での立ち回りだから、距離感がとりづらい。(本来であれば)危なくって無理だよね。それを『だって、万次だから』でやる。ずっと裸足というのもありえないですよ。地下足袋履いてもわからないシーンでも、そういうこと関係なしに、ずっと裸足に草履だけで条件の悪いところでもやっている。クタクタになりながら。それが本当に驚きですよ。素晴らしいですね」
主人公、万次は、どこか木村拓哉その人に重なる気がする。監督はこう指摘する。
「確かに似ていますね。本人がどういうふうに感じて、どう思ってるかわからないですが、自分からすると非常に運命的な役だと思います。(木村と万次は)まったく違うところで生まれ育ってるわけですが、この世の中で同じ空気は吸って生きているのでリンクするってことがあるんだなと思いました。そいういうものと出逢っていく強さがやっぱり必要ですよね。(木村は)すごく特殊で、日本で唯一スーパースターと言える人物だと思いますが、そういう強さがなければ、いま、このようにはできていないはずです」
そして、木村を含めたキャスト全員について話す。
「ただ素敵なだけでは、ただ綺麗なだけでは、役者としてうまく生きていけないだろうと思います。たとえば、ロケの寒い中でやっているほうが、ドキッとする表情を見せたりするんですよね。それはつまり、動物的なところを持っているということだと思うんです。そういうなにか、生きものの強さというものに、僕ら(スタッフ)は撮っているときに助けられる」
動物的といえば、万次の在り方はまさにそうだ。木村は、こんなふうに表現した。
「相手が強ければ強いほど、牙を剥くだろうし、爪も立てるだろうし。ほんとうに動物に近い対応だと思います。ものすごく大きいのは、万次が凜の中に町を感じていたこと。凜を初めて見たときに、町とオーバーラップしてなかったら、あそこまでくいしばって立ち続けることはできなかったと思います。自分が死なせてしまった妹を凜に重ね合わせていたからこそ、そうすることができた。ビジュアルって大事ですね(笑)。ものすごく特別なケースだとは思いますが、土壇場を五万と経験している万次のような人ほど、そんなことにもなるような気がします」
凄まじい活劇が繰り広げられる本作。それは生命を映し出す鏡でもある。監督は言う。
「血は忌まわしいものと捉えられがちだけど、結局は生きている証でもある。暴力って美しいものでもないし、否定すべきものなのでしょうが、その瞬間になにか光るものがあって、どうしても逃れられない人間の本質というか、動物として地球で生きていくための本当の姿が、時代劇では平気で出せるんですよね。ギラギラと。斬り合っていい世界なので」
つまり、『無限の住人』はただの一風変わったフィクションではない。現代を生きるわたしたちにも通じる「何か」が描かれているのだ。
最後に、木村が考える<無限>の意味を訊いた。
「ぼんやり思うことですが、それは<時間>や<時空>ということではなく、<想い>なんじゃないかと。感情ではなく<想い>。個人が抱くことができる<想い>。むしろ、なんで<永遠>って言わないんだろうと思いますけどね。漢字では<限り無き>の<無限>ですからね」