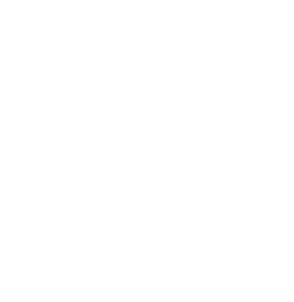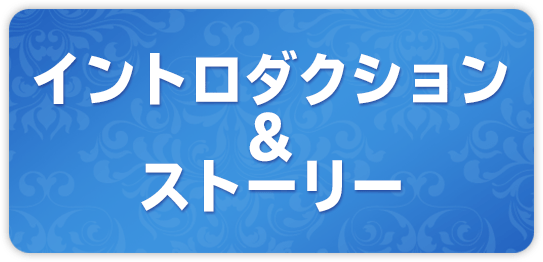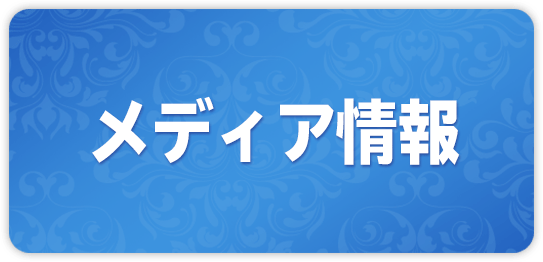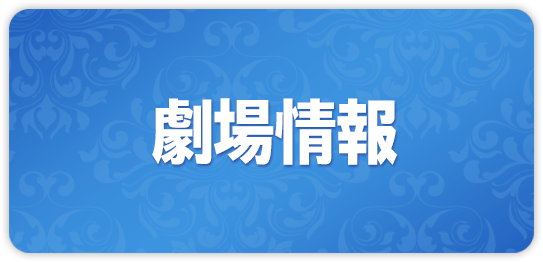中村文則によるサスペンス小説「去年の冬、きみと別れ」に、本作のエグゼクティブプロデューサー=濱名一哉(以下、濱名P)が出会ったのは2014年のこと。美しい文体のもと緻密に張り巡らされた伏線と、後半のまさかの展開に「シンプルにとても衝撃を受けました」と振り返るが、率直に「映像化は難しいだろう」と感じたという。だがその後何度か再読し「愛と憎しみというひとつのテーマが強烈に貫かれている作品。もしかすると新しいサスペンス映画の糸口が見つかるのではないか?」という思いで、C&Iエンタテインメントの久保田修プロデューサー(以下、久保田P)に映画化への話を持ちかけた。「小説としてもかなり実験的。手紙、地の文、あとは証言などで構成されている上、小説だから成立するトリックが用いられている。これを映像にトランスファーするという作業は、非常に困難なことだろうと感じました」(久保田P)。だが濱名P同様、小説の根幹に「愛」を感じたとも。「よく考えると愛に異常も正常もない。そこに線引きはないってことを拠り所にして作っていけば、道は見えるのかなと思いました」。


映画の肝となるキャスティングも、シナリオ作りと並行して進められた。新しいサスペンス映画であると同時に「新しい“スター映画”にしなければ」という思いで、これまでのイメージを180度覆す岩田剛典にオファー。岩田といえば映画『植物図鑑 運命の恋、ひろいました』や、『HiGH&LOW』シリーズの大ヒットも記憶に新しいが、「彼の魅力はそこにとどまらないと感じていました」と濱名P。「ポテンシャルが高く、新鮮でスター性のある人。大変難しい条件ですが、岩田さんならそれが叶うだろう」これまで見せなかったようなハードな描写も多々ある本作だが、岩田サイドは「まさにこういう役をやってみたかった」と、即快諾。そんな岩田を取り巻くキャスト陣も、人気、実力を兼ね備えた面々が集結した。「岩田さんにとって、この作品は本格的な映画俳優としてのある意味デビュー作のような作品になるのかなと。そうすると他のキャストの方々は演技力はもちろん、雰囲気や佇まいなど、俳優としてきっちりと輪郭のある人にお願いしないといけない」(濱名P)。ヒロインとなる百合子は近年女優として目覚ましい活躍を見せる山本美月、耶雲と対立していく木原坂には斎藤工、2人の戦いに巻き込まれていく小林には北村一輝。「山本さんはモデルとしてや女子高生役を演じていたり、若い印象があるかもしれませんが、実は僕らの中では大人っぽい女性のイメージが強かった。ですから、今回の百合子にはピッタリでした。斎藤さんと北村さんにこの役を受けていただいたのは大きくて、岩田さんもお2人に刺激を受けていたと思います。全体のメリハリあるバランスもさることながら、役者さん同士が化学反応し合っていい影響を与え合うのもひとつの狙いでした」(濱名P)。実際、斎藤と北村の確かな演技力と存在感は、岩田のフレッシュな佇まいを前に想像以上のケミストリーを生み出した。特に中盤からは耶雲と木原坂の“対立構造”がひとつの肝になってくるため、岩田と斎藤の相性は重要。2人は『HiGH&LOW』シリーズで共演経験はあったものの、本格的に芝居で絡むのは今回が初。「そういう意味では既視感もなく新鮮な組み合わせ。お2人の火花の散るような演技合戦は、本作の見どころのひとつになってくると思います」(濱名P)。
物語のキーを握る美女2人、朱里と亜希子にそれぞれ浅見れいなと土村芳が扮するのも注目だ。「朱里は普通の人には理解しがたい難しい役だったと思いますが、浅見さんはキャラクターを面白がって演じてくれたと思います。土村さんは芯を食ったお芝居をされる女優さんなので、短い時間の中で圧倒的な説得力を出してくれました」(久保田P)。


記者の耶雲を象徴する印象的なビジュアルとして登場するのが、メガネ。岩田自身「お芝居でメガネをかけるのは初めてで新鮮でした」とのことだが、このメガネもいろいろなパターンを試した結果、本作で使用しているものが採用された。服装も耶雲というキャラクターを表すうえで重要なモチーフであるため、前半はジャケットやかっちり目のシャツを着ながらも記者らしくフットワークの軽さを重要視したカジュアルライクなスタイル、後半はメガネを外し無精ひげをたくわえ、かつ黒ずくめのオーバーサイズ気味のスタイルに変貌していく。遠目から見ると木原坂のように見えるシルエットにもハッとさせられる。
美しい画作りにも定評のある瀧本組だが、今回のカメラマンは撮影監督の河津太郎。「実は佐藤信介監督の『LOVE SONG』(01)の時の助監督が瀧本さんで、撮影監督が河津さんだったんです。それ以来のタッグでしたが、今回は通常の日本映画ではないルックにしたかったので、是非河津さんでいきたいと監督に相談して即決でした」(久保田P)。河津は照明の設計も担当する、日本では数少ない撮影監督の1人。耶雲の心情を表すかのように、スッと陰る美しいライティングなどもすべて河津の完璧な計算の賜物だ。
また木原坂の被写体として何度も登場する美しくも妖しい蝶の写真は、ファッション誌や広告などで幅広く活躍するフォトグラファー=宮原夢画の撮影によるものである。


脚本に大石哲也を迎え、P陣と共にシナリオ作りがスタート。10稿以上重ねたという長い作業の中、時には大胆な原作からの変更を決断することも。登場人物やエピソードの精査はもちろん、主人公を編集者ではなく記者に据え、すべて過去形で語られている原作を一部「リアルタイムで起こっていること」に変更。幸いなことにプロットの段階から中村氏の快諾も取り付け、大胆な脚色を加えたシナリオは新しい『冬きみ』として動き出した。「ある程度脚本の形が見えたところで、瀧本監督にオファーを出し、快諾をいただいたことでさらにこの企画が前進しました。以前『イキガミ』で監督とご一緒した経験から、監督ならこの作品を絶対面白くしてくれるだろうという確信があったんです」(濱名P)。おなじく『イキガミ』で監督とタッグを組んだ久保田Pも「瀧本監督は基本、リアリズムの人。この話は映像化する上では一歩間違えると絵空事になりかねない危うさがあるので、そこを血肉が通ったエモーショナルな物語にするには、人の感情に根付いた演出ができる瀧本監督のような方でないと難しかったと思う」(久保田P)。シナリオ作りに監督が加わり、キャラクターたちがより「生身の人間が演じるにふさわしいもの」に変わっていった。


2017年7月上旬からスタートした撮影は、時間軸が一部逆行する箇所はあるものの、監督の強い要望もありほぼ順撮りで行われた。「監督は岩田さんのために、クライマックスを最終日にしてほしいと早い段階から明確に言われていました。監督は耶雲という難役を演じる岩田さんの環境をどう整えていくかということを、一番に考えられていた気がします」(田中美幸プロデューサー、以下田中P)。岩田への気遣いはもちろん、後々「撮影中は監督が夢に出てくることもありました」と岩田自身が語っていたように主演俳優としての岩田に「静かにプレッシャーをかけることも」(田中P)忘れない。「撮影前半は比較的和気あいあいとした雰囲気で、岩田さんもスタッフやキャスト陣と積極的にコミュニケーションを取られていましたが、後半になるにつれ“集中したい”ということで1人でセットの片隅でじっとしていられることが多かったです」(田口生己プロデューサー、以下田口P)。ある大事なシーンの前日では、監督から「今日は寝ないよね?」と冗談半分、本気半分(?)で言われたという岩田。「はい、寝ません!と(笑)。そういう、なにくそ!みたいな気持ちはいい風に画面に出ていると思います」(岩田)。実際寝不足のせいだけではないだろうが、充血した耶雲のギラギラした瞳がキャラクターにリアルな魂を吹き込んでいるのは確かだ。「監督は表層的なお芝居ではなく、内面からフツフツとマグマのようにたぎるものを作ってほしいと岩田さんに伝えていました。耶雲に強いパッションがないと、この物語のリアリティは支えきれないと監督が誰よりも理解されていたんだと思います」(久保田P)。
そしてスタッフ、キャストが口々に「すごい迫力だった!」と口を揃えるのが、木原坂のスタジオの炎上シーン。消防車が常時待機するなど安全面には十分の配慮をしてはいるものの、想像以上に燃え盛る炎の熱気に内心スタッフは冷や汗ものだったとか。関東近郊の駐車場に作られたオープンセットは、火が回るため天井を抜いているが「ここまで大量に火を使った撮影は僕も初めて」(久保田P)というほどの大規模なもの。昨今CGを使っての撮影が主流になりつつあるが、「本物の炎を使いたいというのは監督のこだわり。生身の役者さんに炎の熱さを感じて、リアルな環境で芝居をしてほしいということでした」(田口P)。 また作品のひとつの肝となるのが、耶雲と木原坂の対決シーン。北村が率先して声をかけ岩田、斎藤の3人で撮影後半に食事に行く機会も得たという2人だが、この日は撮影合間も言葉を交わすことは少ない。真っ赤な光に包まれた暗室の中、静かに木原坂を挑発する耶雲と、初めて感情を露わにし激高する木原坂の息詰まるやり取りが粛々と撮影されていく。岩田の胸ぐらをつかむ斎藤に「もっと強めにつかんで」、対する岩田には「つかまれても目はそらさないで。強い眼差しのままで」など、細かいニュアンスまですべて直接指示していく監督。終始心地いい緊張感が漂う撮影日となったが、珍しく岩田がセリフを噛んだ後は「すみません」とお茶目に舌を出し、一瞬だけ現場が和むことも。
そして後日、いよいよ迎えた岩田のオールアップ日は、最後まで緊張感が途切れないクライマックスシーン。あるキャラクターの悲痛な絶叫がスタジオ中に響き渡る中、今まで見せたことのないような冷たい表情を浮かべる岩田の横顔はゾクッとするほどに美しくスクリーンに切り取られている。「今回は本当に大変な現場で、常に俳優として修行しているような撮影でした。北村さんにも“よくこんな大変な役を引き受けたな”と言われましたし、夜寝ていても監督が夢に出てきて演技指導をされるんです(笑)。こんな体験は生まれて初めてでしたが、撮影がすべて終わった日は現場から立ち去りたくなかった。それだけ作品に入り込んでいたんだなと思いましたし、僕にとっては本当に大きな作品になりました」(岩田)。


強い印象を残す劇中歌「Make You Feel My Love」は田中Pの発案で満場一致で決定。「ボブ・ディランのオリジナルが一番有名かと思いきや、最近だとアデル版も有名なんです。既にスタンダードになっている楽曲で、何より歌詞……“何があっても愛し抜く”という内容が本作に驚くほどピッタリでした。劇中歌が撮影前に決まったことで、その後の作業もすごく楽になりましたね」(久保田P)