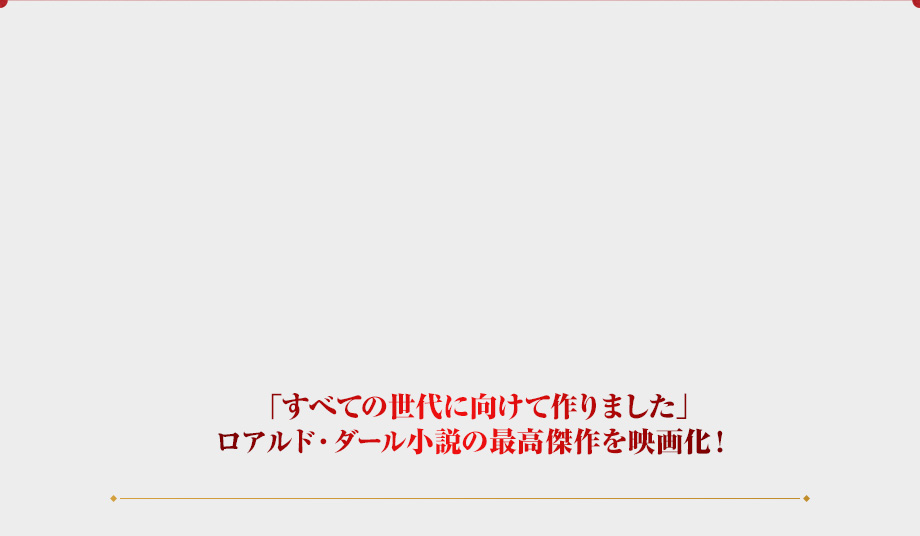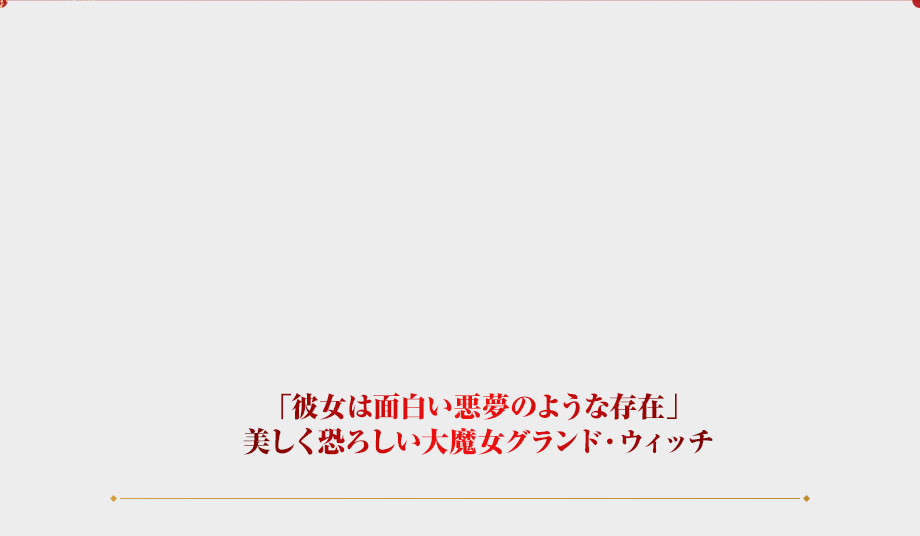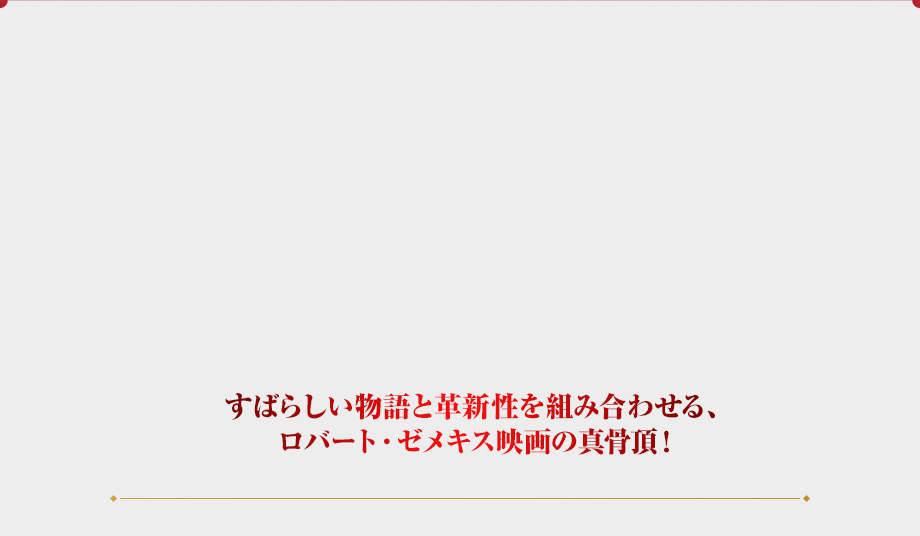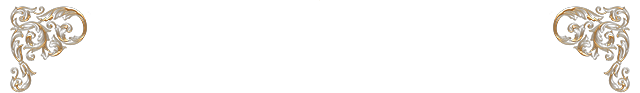
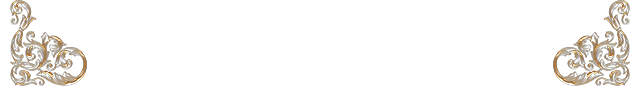
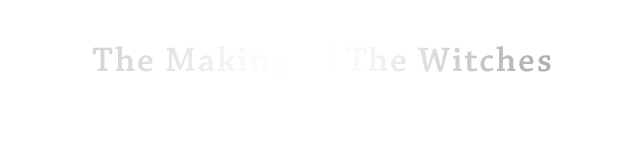

ロアルド・ダール原作の『魔女がいっぱい』は、秘密の魔女集会に足を踏み入れてしまった少年“ぼく”の活躍を描いたファンタジー小説。愛情深いおばあちゃんの助けを借りながら、“ぼく”は魔女たちの邪悪な計画を阻止しなくてはならない。巨匠ロバート・ゼメキス監督の手にかかったこの物語は、観る者を没入させるファンタジー体験をもたらす。
 「悪魔的な魅力がある物語です」と笑顔で話すのは、監督・共同脚本・製作を務めたゼメキス。今回、みんなに愛されているこの小説を映画化できるチャンスにワクワクしたと監督は話す。「子ども向けの良い本は、本当に子ども向けの本というわけではなく、ロアルド・ダールの小説も例外ではありません。子どもが主人公として描かれているので、もちろん子どもが楽しめる本ですが、ダールの描く物語はあらゆる世代の読者が楽しむことができます。『魔女がいっぱい』はロアルド・ダールの最高傑作のひとつ。だから私はとくにこの本の映画化に興味がありました。すべての世代の人に向けてこの映画を作りました」。
「悪魔的な魅力がある物語です」と笑顔で話すのは、監督・共同脚本・製作を務めたゼメキス。今回、みんなに愛されているこの小説を映画化できるチャンスにワクワクしたと監督は話す。「子ども向けの良い本は、本当に子ども向けの本というわけではなく、ロアルド・ダールの小説も例外ではありません。子どもが主人公として描かれているので、もちろん子どもが楽しめる本ですが、ダールの描く物語はあらゆる世代の読者が楽しむことができます。『魔女がいっぱい』はロアルド・ダールの最高傑作のひとつ。だから私はとくにこの本の映画化に興味がありました。すべての世代の人に向けてこの映画を作りました」。
映画のなかの魔女たちは、みんな美しいに魅力に満ちた人間の女性に見える。誰もほうきに乗るとは想像もできない。アン・ハサウェイは、そのなかでも最高に洗練された魔女たちのリーダーである大魔女<グランド・ウィッチ>を演じた。「ロアルド・ダールは、誰よりも魅力的に恐ろしいキャラクターを描く。そして私たちが普段見かける、よく知ったものに悪を植え付ける。だから面白くもあり怖いのです」。ハサウェイはゼメキスとのコラボレーションにワクワクしたと言う。「ゼメキス監督は、繊細なユーモアとリアルな感情を描くことができる。いま技術的に何が可能かについてのルールを定義したのもゼメキス監督です。彼の想像力と技術レベルをもって、ロアルド・ダールの物語と融合させれば、興奮冷めやらぬ組み合わせになるのは当然だと思います」。
美しい魔女を身の毛のよだつ存在に変えたり、人間を愛らしいねずみに変身させたりする。ストーリーとファンタジーの要素の融合が、ゼメキス監督をこの映画に大きく惹きつけた。そして監督は、ロアルド・ダールの物語の核にある“人間らしさ”というテーマにも共感した。「この物語の真のテーマは、それぞれの個性を受け入れること、そして自分らしくあることを認めることです。それは、本当の自分を探し認める旅。だからこそこの物語は、時代を超えてさまざまな世代の読者に愛され続けているのだと思います」とゼメキス監督は話す。
製作陣はこの物語や登場人物に忠実でありながら、舞台をヨーロッパからアメリカのアラバマ州に移した。そして時代も現代にするのではなく、1960年代の設定で脚本が執筆された。「そうすることで、物語をよりチャーミングな形で伝えられると思いました。60年代には、携帯電話も24時間稼働の監視カメラもありません。そして一番大事にしたのは、原作のトーンを保つこと。それが鍵でした」とゼメキス監督は説明する。製作のジャック・ラプケはこう話す。「ロアルド・ダールが最高の作家のひとりであることは間違いありません。彼の物語は、子どもの視点から書かれているので、子どもにもわかりやすい。しかし、彼の皮肉的なユーモアのセンスは、大人も楽しめる。それをゼメキス監督独自の物語づくりと融合させることで、さまざまな世代の観客に素晴らしい体験を提供できる映画になると思いました」。


大魔女<グランド・ウィッチ>は、白くなめらかな肌や完璧に形作られた頬骨、アーチ形の黒い眉、血のように赤い唇をもつ、ひときわ美しい存在。しかし外見的な美しさとはうって変わり、彼女の心は闇深い。ロアルド・ダールが作り出したキャラクターのなかでも、最も記憶に残り、最も恐ろしい悪役ともいえるこの役を今回、アン・ハサウェイが演じた。
 ハサウェイは小さい頃、ロアルド・ダールの本が好きだったという。「お気に入りのロアルド・ダール作品はたくさんあります。物語のなかにある優しさ、子どもたちが感じる感情がリアルで感傷的でないところも、とても素晴らしいです。子ども向けの本では、すべてをばら色のもやを通して描くことがありますが、『魔女がいっぱい』をはじめとするロアルド・ダール作品の中の子どもたちは、物事を明確に見ている。それが新鮮でした」。大魔女<グランド・ウィッチ>について、ハサウェイはこう説明する。「グランド・ウィッチの存在は完全なる悪夢。でもそれは、とてもおもしろい悪夢。彼女はすべてを忌み嫌っています。彼女の人生には喜びがまったくありません。そして世界がとてつもなくひどい場所だと感じている。だからほかの人にも、できるだけ多くの痛みを引き起こそうとする。その方法は、最高に素敵なんです!」。
ハサウェイは小さい頃、ロアルド・ダールの本が好きだったという。「お気に入りのロアルド・ダール作品はたくさんあります。物語のなかにある優しさ、子どもたちが感じる感情がリアルで感傷的でないところも、とても素晴らしいです。子ども向けの本では、すべてをばら色のもやを通して描くことがありますが、『魔女がいっぱい』をはじめとするロアルド・ダール作品の中の子どもたちは、物事を明確に見ている。それが新鮮でした」。大魔女<グランド・ウィッチ>について、ハサウェイはこう説明する。「グランド・ウィッチの存在は完全なる悪夢。でもそれは、とてもおもしろい悪夢。彼女はすべてを忌み嫌っています。彼女の人生には喜びがまったくありません。そして世界がとてつもなくひどい場所だと感じている。だからほかの人にも、できるだけ多くの痛みを引き起こそうとする。その方法は、最高に素敵なんです!」。
舞台はアメリカに移されたが、グランド・ウィッチの出身は原作に忠実にノルウェイ。そのためハサウェイは、自身のリサーチとアクセントコーチの助けもあり、ノルウェイの古ノルド語にたどり着いた。「詩について説明している学者の映像を見つけ、古ノルド語を話すとき、Rの発音で舌を巻いていました。とても魔法的な響きでした。学者は牧場の羊の話をしていましたが、アクセントのおかげでその物語が壮大で、恐ろしく、ドラマチックに聞こえました。だからその話し方を真似したんです」とハサウェイは説明する。その後、ゼメキス監督に確認してもらったとき「原作本から直接、監督はベーコンの焼ける音を私に教えてくれた。それを古ノルド語のアクセントと混ぜ合わせて、グランド・ウィッチのアクセントができました」と振り返った。
衣装とヘアメイク担当は、本作に登場する50人の魔女たちそれぞれの個性を掘り下げ、ビジュアルを決めていった。その結果は、1950年代後半と1960年代初頭の印象的な融合となった。魔女たちの最終的なビジュアルは、映画の舞台の時代、魔女の役と演じる役者の性格、シーンでのスタイルの役目など、複数の要素を合わせて決められた。そして魔女は飛ぶ。「アンはワイヤーに吊るされたり、飛ぶアクションをすべてこなしたりすることにも乗り気でした」と製作のラプケ。『魔女たちの上に浮かんでダンスするのはどう?』と私が提案したら、ほとんどの人は私の頭がおかしくなったと思うと思います」とハサウェイは笑う。「でも、無限の想像力と、それを可能にする革新的な技術の知識があるゼメキス監督は、『そうだね、おもしろそうだ。どうやればいいかわかるよ』と言って、実現してくれました。だから『すばらしい! ありがとう!』と、とても嬉しかったです」。


すべてのロバート・ゼメキス監督作品では、革新的な技術が現実的な物語と真の意味で融合する。このロアルド・ダール原作『魔女がいっぱい』では、視覚効果チームにふたつの異なるチャレンジがあった。それは、環境をつくることと、アニメーションをデザインし制作すること。製作陣はロケーション撮影ではなく、セットを建築し撮影することを選んだため、どのセットを実際の建物にして、どのセットをデジタルにするか、早い段階で決めることができた。視覚効果監修のベイリーはこう説明する。「間違いなくデジタルで作るべきものもありました。実際のスペースの高さに制限があったりしたので、6メートル以上のものはポストプロダクションで作ることに。同じように、換気ダクトのなかなどはスペースが狭すぎてカメラが入れないため、デジタルで作る必要がありました。それでも、できる限りカメラで撮影することにこだわりました。複雑なダンスホール、ダイニングルーム、キッチンのシーンでは、画面のなかの要素に触れられるような感覚をもたせたいと思ったからです」。
 ゼメキス監督にとっての鍵となったのは、ネズミに人間のときのキャラクターの性格を保たせ、ネズミに変身させられたあとのそれぞれのキャラクターを、誰が観てわかるように、俳優としての力を発揮してもらうことだった。「物語のヒーローたちはネズミに変身させられるが、話すことはできます。だから、人間のキャラクターの性格を保つことができる。だが彼らの肉体は、本物のネズミになってしまっているので、ネズミの目や眉の形を少し変えて、各俳優が演じる役が反映されるようにました」。
ゼメキス監督にとっての鍵となったのは、ネズミに人間のときのキャラクターの性格を保たせ、ネズミに変身させられたあとのそれぞれのキャラクターを、誰が観てわかるように、俳優としての力を発揮してもらうことだった。「物語のヒーローたちはネズミに変身させられるが、話すことはできます。だから、人間のキャラクターの性格を保つことができる。だが彼らの肉体は、本物のネズミになってしまっているので、ネズミの目や眉の形を少し変えて、各俳優が演じる役が反映されるようにました」。
ゼメキス監督と長年仕事をしてきている視覚効果監修のベイリーはこう話す。「ゼメキス監督は視覚効果のマジシャンです。作る映画すべてにおいて彼はテクノロジーに興味を惹かれていると思うけど、テクノロジーを使うこと自体に興味があるのではなく、物語を伝えるのに役立つか、またテクノロジーを使うことで物語がより良く伝えられるようになるかを考えています。彼はパートナーとして携わり、視覚効果制作のプロセスを理解しようとしてくれました。物語を描く際に重要となる部分で、革新的な技術を使ったヒーローレベルの仕事ができたと感じています」。
すばらしい物語づくりと革新性を組み合わせるのは、ロバート・ゼメキス映画の真骨頂。とくに、子どもから祖父母まで、その間の全員を含めた幅広い観客に訴える映画をつくるとき、それは遺憾なく発揮される。ロバート・ゼメキス監督は、「子どもにとって最高の映画は、大人にとってもすばらしく楽しめる映画です」と話す。おそらくロアルド・ダールの哲学もこのような考えに基づいていたと想像に難いが、「子どもが楽しめる映画を作る鍵は、子どもを過小評価しないことにあると思います。だから8歳から80歳まで全員が楽しめる映画を作ればいいだけなんです」。