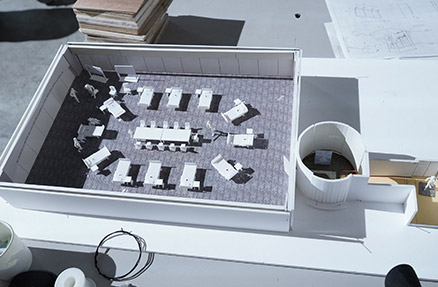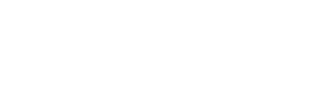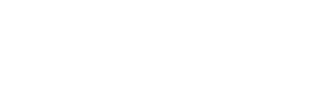企画開発 大逆転ムービーをやりたい


2015年、叙述トリックを用いた傑作小説の映画化『イニシエーション・ラブ』の成功に、再び大逆転ムービーをやりたいと堤幸彦と飯沼伸之プロデューサーは企画を考え始めた。
そこで出会ったのが、冲方丁の「十二人の死にたい子どもたち」。高いサスペンス性、大逆転のある展開、さらに未成年たちの心の機微が描かれている点が魅力的であった。脚本は舞台で活躍し、多ジャンルの脚本を手がけ、理系脳で構造のしっかりした脚本も得意とする倉持裕に決定。
そこまではトントン拍子だった。
ところが、そこから脚本開発が困難を極めた。なにしろ、原作の内容が複雑で、原作の良さを余すところなく残したうえで2時間ほどにまとめるのは至難の業。原作を読み込み、構造分析し、解体し再構成を繰り返して、2年近く練った末、最終稿があがったのがクランクイン直前、2018年6月だった。