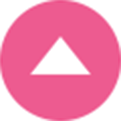「映画館を舞台にした映画を作るのであれば、映画愛に溢れたものにしたい」という稲葉プロデューサーの想いから、劇中ではさりげなく過去の名画へのオマージュがちりばめられている。映画に魅せられ映画監督を目指す健司と劇場館主の本多の関係性は『ニュー・シネマ・パラダイス』、そして映画の世界と現実の世界を繋ぐファンタジックな設定は『キートンの探偵学入門』『カイロの紫のバラ』、王女と身分違いの青年が恋に落ちるのは『ローマの休日』、落雷によって変化が起きる設定は『バック・トゥ・ザ・フューチャー』、劇中劇「お転婆姫と三獣士」のモデルは『オズの魔法使い』『狸御殿』シリーズ、北村一輝が演じるスター俳優・俊藤龍之介の愛称“ハンサムガイ”は日活のガイシリーズ……など、全く同じシチュエーションということではなく、それぞれの映画のエッセンスが上手く物語にとけ込んでいる。なかでも特に印象的なのは、美雪と健司のガラス越しのキスシーンだろう。これは『また逢う日まで』のオマージュなのだが、触れたいけれど触れられない2人というこの映画の設定にうまく活かされ、とてもピュアで美しいシーンとなった。
また、この映画の時代設定が1960年であることにも理由がある。それは、映画からテレビへと変わりゆく時代だったということ。カラーテレビの放送が始まったのが1958年。1960年は映画の観客数が急激に減り始めるまさに転換期だった。時代の変化とともに皆の記憶から忘れられていった映画たち。本作ではそんな映画たちへの想いが込められている。

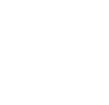


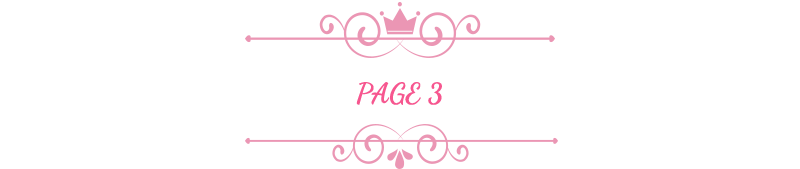





 @romance_gekijo #ロマンス劇場
@romance_gekijo #ロマンス劇場 @romance_gekijo #ロマンス劇場
@romance_gekijo #ロマンス劇場